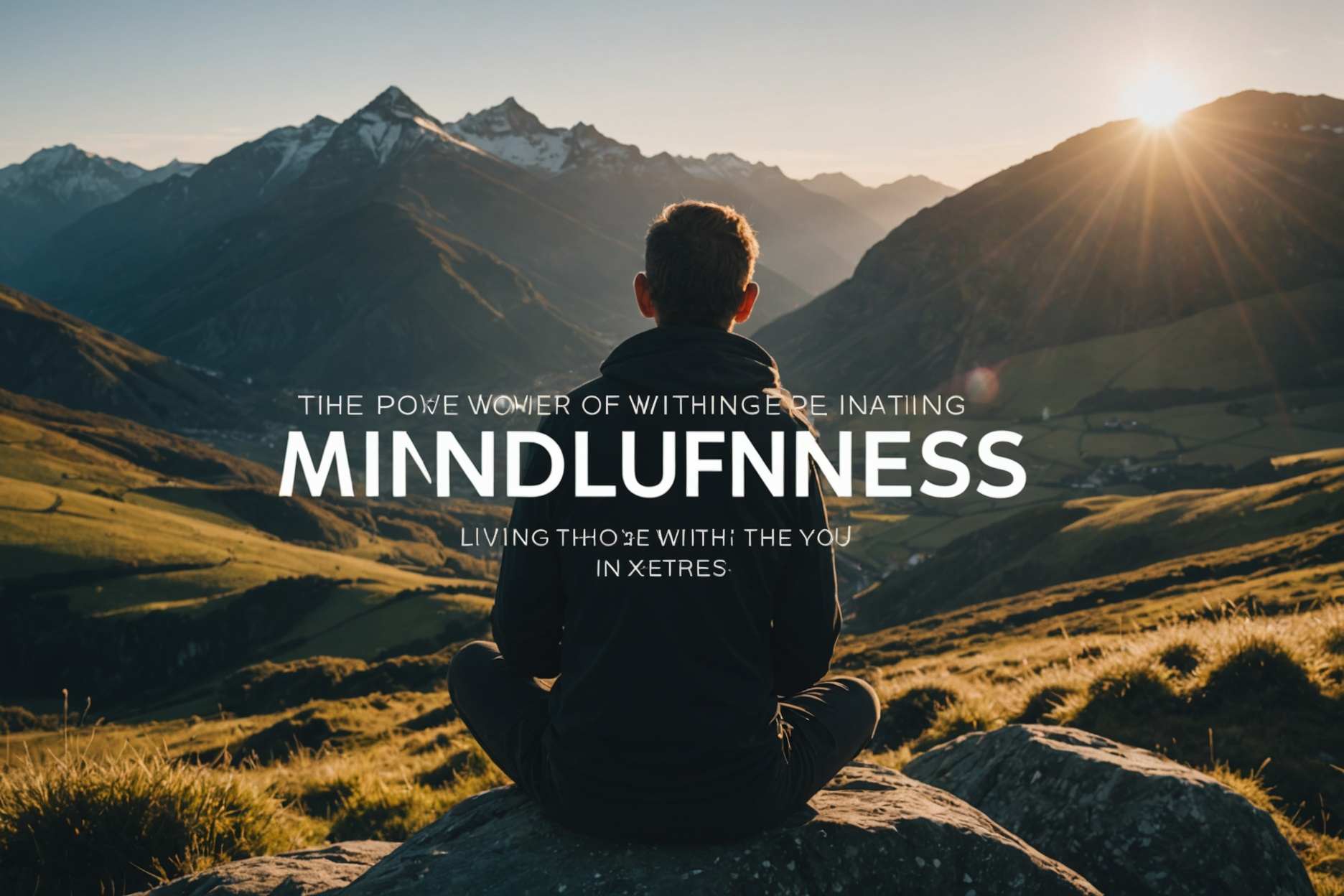長時間労働の問題や少子高齢化を背景に世界で注目されるようになった、「ワーク・ライフ・バランス」。日本では2007年に憲章が策定され、官民一体となって取り組みを進めてきた。約20年たった今年、女性初の総理大臣となった高市早苗首相が「ワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てて働く」と表明したことで、改めて「ワーク・ライフ・バランス」に注目が集まっている。20代から仕事にまい進してきたというタレントのホラン千秋さんに受け止めを聞いた。(全2回の1回目/後編へ続く) 【写真】金髪ヘアがチャーミング!ホラン千秋さんをもっと見る * * * ――ホラン千秋さんは、20代後半の2017年から25年3月まで、TBS系の夕方の報道・情報番組「Nスタ」でキャスターを務めた。ニュースに携わった8年の間に、第2次安倍晋三政権、菅義偉政権、岸田文雄政権、石破茂政権と四つの政権について報じてきた。 総理大臣のスケジュールは「首相動静」といって、記録が一般に公開されています。それをチェックすれば、どの首相も本当に休みなく働いているということが一目瞭然です。それは高市早苗首相も同じで、「ワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てる」とあえて口にしなくても、そもそも“総理”という役職に就いた瞬間から「ライフ」という概念は存在しないくらい、みなさんお忙しかったと思いますね。 それでも、なぜ言葉にしたのか。それはあえて明確に言葉にすることで、ご本人の覚悟を示したかったのだろうなと私は受け止めました。同じことを心に決めていても、言葉にするのとしないのとでは国民に届くメッセージは大きく変わってくる。どう「パフォーム」するのかというのは、政治家にとって大切な要素です。 また高市さんは、女性初の首相としても注目されています。自民党内はもちろん世間からもさまざまな反響があったはずです。どんな声があったとしても、自分はやるべきことをやっていく。そんなメッセージだったのではないでしょうか。時代が違えば、もしかしたら高市さんはまた違う表現をしていたかもしれません。 そもそも私たちのような一般社会の労働者と首相の感覚を同列で語ってもいいのだろうか、という思いもあります。文字通り国を背負う激務ですからね。それを踏まえたうえで、自民党の置かれた状況や、高市さんをイチ政治家として見たとき、個人的にはその発言に違和感はありませんでした。
ただ、一国のリーダーがそうしたメッセージを発することで醸成される空気があることは事実です。ワーク・ライフ・バランスの大切さが叫ばれている時代に、それを捨てると言い切られてしまえば、推進してきた省庁や国民が戸惑うこともあるでしょう。 海外では、議員の方が国会に子どもを連れてきたり、ニュージーランドのアーダーン元首相のように就任期間に産休を取得したりするケースもありました。もしかすると、そういう形でメッセージを発信していくことが、今の時代の「正しさ」なのかもしれません。ただ、人間は画一的ではないし、こうあるべきだと言い切ることはできないとも思います。 ――世代によって言葉の受け止め方は異なるのだろうか。 どう響いているかは、その世代でないとわからない気がします。どんな時代を生きてきたかで感覚はこうも違うのかと思い知らされる日々ですから。時代が売り手市場なのか、買い手市場なのかでも変わってくるし、就職氷河期で就職先を選べなかった世代からすれば、1社で勤め上げることが当たり前。一方で今は転職へのハードルも低くなり、数社経験することも普通の時代です。仕事のために人生があるのではなく、人生を豊かにする手段として仕事があると考えている人も増えています。若い世代にどう響いたのか、個人的にも聞いてみたいですね。 ――自身は1988年、東京に生まれた。6歳のころからキッズモデルをはじめ、14歳で今の事務所に所属。大学在学中は民放キー局の新卒採用を受けるも全て不採用だった。タレントとして仕事をはじめたころは、「生活のすべてがワークだった」と振り返る。 20代前半は体力もあれば、やる気もある。「もっとできるようになりたい」「認められたい」というエネルギーが湧き出る時期でもあります。特に私の場合は小さいころから夢見たことを仕事にできたので、どこか文化祭の延長のような興奮状態というか、自分が大好きで追い求めていたものを続けられる喜びがありました。休みがほしいと思ったことも、自分の時間が労働に搾取されているという感覚もありませんでした。その結果、ワークに没頭する形になりましたが、それが幸せだったし、打ち込む楽しさを感じていました。
プライベートで会う相手も仕事の仲間ばかり。でもそれが楽しかったんですよね。ワークとライフが密接に関係していて、周りから「仕事だけして幸せなのか」と聞かれたこともあります。でも、私にとっては好きなことをしているだけだし、仕事=自己実現の真っ最中だった。なので、そう聞かれる度に違和感がありました。 ――収録から収録へ。求められることに応えようと全力だった。その総量を意識したことはないが、24時間ずっと仕事のことを考える日々を過ごした。 一番ハードな時期は年に10日も休んでいないということもありました。それに寝ているときも夢に仕事のことが出てくるんです。生放送に遅刻する夢もしょっちゅう見たし、それは今も変わりません。私たちタレントは機会が与えられないと働けない職業ですから、仕事をいただけることが幸せだったし、だからこそ頑張れたのだと思います。 ――だが、ある時期から「仕事があるだけ幸せ」という言葉に対して、素直に「そうだよな」と思えなくなったという。 気力はあるのに、体力が追いつかなくなったんです。それまでは一日にいくつ仕事を入れていても、ガッツや根性で乗り越えることができました。それが、少しずつ疲れが取れないと感じるようになり、やる気だけでは乗り切れないと思うことも増えていきました。 疲労は仕事のパフォーマンスにも影響しました。それまでは失敗したとしても自分なりに理由を分析できたし、次への伸びしろだと捉えていました。それが、「どうしてこんな失敗をしてしまったんだろう」と思うことが増え、失敗の内容に自分が納得できないことが増えた。その状態が続くうちに体力も心もすり減っていき、この働き方では持続不可能だと思いました。 やりたい仕事はたくさんあっても、身体はちゃんと経年劣化で老いていく。周りから指摘されたわけではなく、自分の納得度と照らし合わせたときに、到達していないと思ったんです。 納得のいくパフォーマンスでお返しできないなら、一つずつのクオリティーを下げないことを優先したい。会社とも相談し、現場仕事は一日に2個までと決めて、持続可能な働き方を模索しはじめたのが、30歳になるころでした。 (構成/AERA編集部・福井しほ)
福井しほ
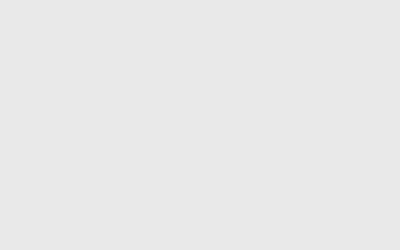 Figure out how to Amplify Your Open Record Reward
Figure out how to Amplify Your Open Record Reward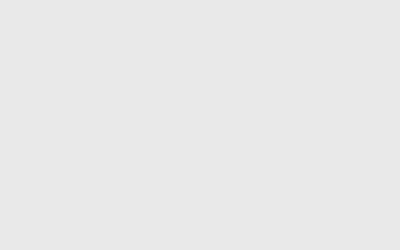 Iran begins cloud seeding to induce rain amid historic drought
Iran begins cloud seeding to induce rain amid historic drought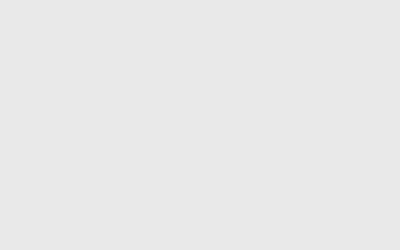 Step by step instructions to Guarantee Your Internet Promoting Degree Supplements Your Profession Objectives
Step by step instructions to Guarantee Your Internet Promoting Degree Supplements Your Profession Objectives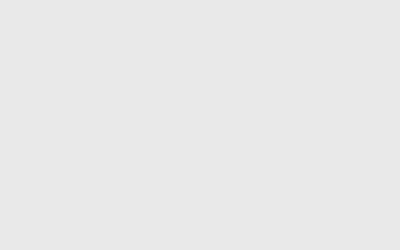 10 Activities to Lift Your Consume and Bust Your Stomach
10 Activities to Lift Your Consume and Bust Your Stomach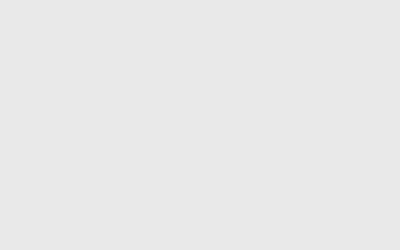 The Force of Care: Living with Goal
The Force of Care: Living with Goal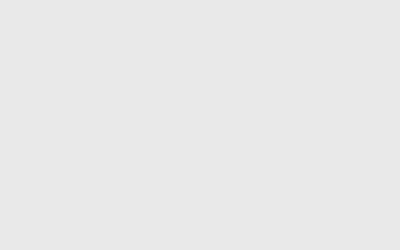 Manual for Vegetarian Protein Powder
Manual for Vegetarian Protein Powder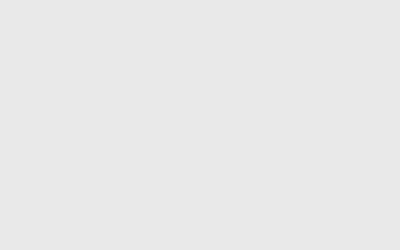 【フィギュア】坂本花織「あらまぁ」今季世界最高、真央に並ぶNHK杯4度目V&ファイナル確定(日刊スポーツ)
【フィギュア】坂本花織「あらまぁ」今季世界最高、真央に並ぶNHK杯4度目V&ファイナル確定(日刊スポーツ)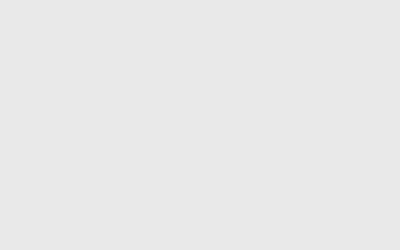 Remote Work Survival manual: Helping Efficiency at Home
Remote Work Survival manual: Helping Efficiency at Home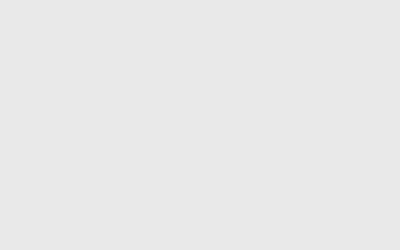 From Overpowered to Coordinated: Individual Accounts of Cleaning up
From Overpowered to Coordinated: Individual Accounts of Cleaning up